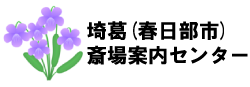個人で行うのには難しい葬儀を公的な施設を利用して行う
葬儀で久しぶりに親戚と集まることが多い
多くの場合、葬儀には親戚が集まることになります。お通夜や告別式とは違い、葬儀式は親戚などの近親者のみで行うことが多いです。
葬儀のひとつの役割として、このように親戚一同が介し旧交を温めるというものがあります。普段生活している中で親戚一同が集まるのは、結婚式、葬儀式、法事くらいでしょう。伝統的な習慣が残っている場合、正月に親戚が集まるということもあるかもしれませんが、そうした風景というのは現代の日本ではもうあまり見られない光景になってきています。
なぜ葬儀などで集まらなければならないのか
親戚が集まるメリットとしてあらためて自分のルーツを確認できるという点や兄弟、従兄弟などの現行を確認することができるというものがあります。それぞれが家庭を持ち生活をしていると日頃の雑事に追われてなかなか連絡を取ることができないというのが現状です。そうした中で同じルーツを持つ人と集まることができるというのは非常に貴重な機会でもあります。
日本のシステムが家や血縁を中心に考えられているのは
旧来の日本の文化として家を中心に考えるというものがありました。実はこうした発想の根底には明治時代に作られた法律があります。国を国家と呼びそれぞれの家の集まりが国であるという思想は、明治時代の民法に垣間見ることができます。
そうした家を中心にした社会制度は現在では非常に薄くなっています。高度経済成長期に学校や会社など自身の所属を中心とする文化を経て、現在では個人を中心とする文化へと変化しつつあります。
葬儀の文化などもそれらの社会全体の様子に非常に大きな影響を受けています。供養難民という言葉や家族葬の増加がそのひとつの現れでしょう。文化の変化は少しずつこれまでの集団を中心とした文化に浸透していき、これまで家や会社などの集団を中心に考えられていたシステムは少しずつ変容しつつあります。
葬儀は亡くなった本人には行えない
こうした社会の流れの中で、縁というものをこれまで以上に注視していかなければならなくなりつつあります。その他の全てのことが自分でなすことができたとしても、葬儀と供養といった死後の跡片付けだけは絶対に自分では行えないからです。どれほど綿密に準備をしていたとしても自身が死んでしまったという事実に気づいてもらわなければ何もはじまらないのです。
また現行の法律上、もし身寄りなく亡くなった場合には親戚などに連絡がいくことになります。面識があればまだしも、数十年もあったことのない親戚という風では対応を拒否したくなるのも無理もないでしょう。
2010年に放送されたNHKのテレビ番組「無縁社会」では、全国で年間3万2千体の引き取り手のいない遺体があることが述べられていました。その中には近親者として甥や姪が見つかったものの生前の面識がなく突然の遺体や遺骨の引き取りの連絡に戸惑う声がありました。
個別化・私事化が進んだ結果、葬儀は不必要なものとして見られることも増え、全国的には1割、東京では2割となっています。また家族葬は全国的に4割、東京では半分以上が家族葬の形式で行われています。
この傾向が更に進み、直葬の形式が多くなれば、それだけ親戚に会う機会は少なくなり、血縁者との関係もさらに薄くなっていきます。そこまで行きついてしまうと葬儀自体が崩壊し、遺体を処理するという最低限の葬儀の役割も果たされなくなっていってしまう可能性すらあります。
現在では公営斎場など葬儀に関することでも多く自治体によってサービスが提供されています。それは個人ではなかなか誰かが亡くなったときに迅速に対応することが難しくなってきたことの裏返しでもあります。もし葬儀を行わなければならなくなったときにはこうした公共の福祉を利用し負担なく葬儀を行うというのも一つの方法ではないでしょうか。